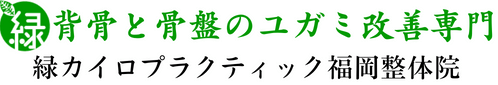めまい
あなたのめまいが治らないのはわけがあります。
下記のようなめまいのある人に特に効果的です

- 何年も薬を飲み続けているめまいが治らない
- MRIなどの検査をしても脳に異常がないのにめまいがある
- 病院で自律神経失調やうつ病と診断された
- スポーツや仕事等で首に負担がかかっている
- メニエールと診断されたが難聴などはない
など、なかなかめまいが改善しない方はぜひ、当院を試してみてください。
カイロプラクティックはめまいの改善が症例が多いです。
病院での検査で脳に問題がないのにめまいがある場合は
【首の骨のゆがみと首まわりの筋肉の問題】がほとんどです。
首の骨がゆがんでいる場合は、必ず腰椎(腰の骨)も検査する必要があり
腰の骨のユガミは骨盤のユガミから引きおこされることがほとんどですから
骨盤も検査する必要があります。
めまいをほおっておくと、生活に支障が出ます。
なるべく早く解消することをおススメします。
カイロプラクティックによるメニエール病の施術は
- 頚椎の調整:特に頚椎2番のアジャストメントを行い、神経伝達を改善し、頚椎付近の硬直やしこりを軽減します
- 体の歪みを整える:血流やリンパの流れを改善し、全身のバランスを整えます
- 内耳(バランス感覚)の調整:めまいの原因となる内耳の機能を整えます
- 自律神経の調整:ストレスや疲労による自律神経の乱れを改善します
- お腹のほぐし:自律神経と内臓の関係に着目し、お腹のしこりをほぐすことで自然治癒力を引き出します
これらの方法を組み合わせて施術することで、めまいや耳鳴りなどのメニエール病の症状が軽減される可能性があります。ただし、効果には個人差があり、即効性というよりも徐々に改善していく傾向があります
よくある質問
- 何回くらいで治りますか?みてみないと分かりませんが、最初の5・6回で効果を実感できるはずです。
病院でも原因がはっきりしないめまいの原因は
肩こり・首こり
長時間の首の筋肉の緊張が、脳の血流を圧迫することでめまいがおきます。
不良姿勢
首の問題がおきる原因としてパソコン作業等による不良姿勢があります。
顎の関節の問題
顎の筋肉の緊張は首の筋肉に伝わり、首こりやめまいの原因となります。
ストレス
ストレスによる自律神経のバランスが乱れでめまいがすることもあります。
ホルモンバランス
ホルモンバランスが乱れから、交感神経優位が続くと血管が収縮しめまいがすることもあります。
その他の誘因
自宅でできる対処法
悪い姿勢をやめる
テレビを見るときに、首をねじったまま見る。パソコン環境を考える
ストレスを減らす
睡眠不足・暴飲暴食・仕事がんばり過ぎ・人間関係のストレスなどを減らす
目の負担を減らす
スマホの見過ぎ、メガネの度の調整
などなど
良性発作性頭位めまい症
予防法
①横向き寝でいつも同じ側ばかり下にして寝ない
②頭を高くして頭の位置を変える
➂意識的に寝返りを打つ
前庭神経炎
前庭神経炎は、感冒の後などに起こるめまいです。
ウイルス感染が関与しているとも言われていますが、原因はわかっていません。
ひどい回転性めまいと嘔気が数日間続きます。
ひどいめまいが収まっても、軽い浮動感が数ヶ月続くこともあります。
メニエール病
メニエール病の原因はずばり「内リンパ水腫(内耳のリンパが増え、水ぶくれの状態)」です。
その根底にはストレス・睡眠不足・疲労・気圧の変化・几帳面な性格などがあると考えられています。
めまい=メニエール病と考えがちですが、メニエール病には診断基準があります。
それは「難聴、耳鳴り、耳が詰まる感じなどの聴覚症状を伴うめまい発作を反復する」です。
「反復する」という点が大事で、めまい発作や難聴発作が1回起きただけではメニエール病とは診断できません。
この診断基準を満たし、かつ類似の他の病気を除外できたものを「メニエール病確実」と診断します。
メニエール病と診断されたら、薬物療法による対症療法が中心になります。
症状の種類や重さに合わせて、血流改善剤・利尿薬・精神安定剤・自律神経調整剤などを用います。
ひどい発作が起きたときは、点滴または注射を行います。
利尿効果を目的として、水分を普段より多めにとるという飲水療法をすすめている病院もあります。
以上は耳からくるめまい3つ。これらは耳鼻科に行く。日本めまい平衡器学会のHPをチェック
脳幹や小脳に起きる脳卒中(脳梗塞など)が原因の場合
救急車を呼ぶ
薬による治療
耳からくるまめいとの鑑別
めまいとともに
- 物が2重に見える
- うまく言葉が出ない
- 片半身がしびれる
神経内科や脳外科に行く
めまい以外の症状が出るときは、救急車を呼ぶ
めまいを引き起こす16分類にあてはまらない2割のまめいはめまい症と言われる
めまい症の3分の2はPPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい)
誘因
- 立っているとき
- 不安定な動画を見た時
- 急な振りむき
- 陳列棚をみる
- 激しい動きの画像を見る
- 丸椅子に座る
- スクロール画面を見る
- エレベーターンに乗る
など
薬で過敏な反応をおさえれえる